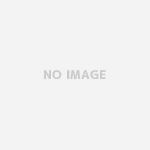最初から少しインパクトの強いタイトルですが、これはブログを始めようかなと友人に話したところ、ぜひ書いてほしいと言ってくれたものです。
僕は学校という場では写真を学んでおらず、スタート時点から仕事の中で毎度、壁にぶち当たりながらほぼ独学で写真と向き合ってきました。
そのため一般的な写真の定義とか解釈とは異なる視点での言葉も多いと思います。
さらに言えば、10年以上に渡り写真に携わっていながら、常に写真表現自体へ疑問を感じているという不思議な関わり方をしてきたので、一つの特異な意見資料としての価値はあるかもしれないなと思いながら綴っていこうと思います。
本当に写真は死んでいないのか
写真との微妙な距離感を保っている僕が写真の今を俯瞰してみてみると、果たして本当に写真は死んでいないのだろうかと思います。
きっと友人は数多くの新しいメディアが生まれていく現代でも写真という表現はなくなっていないし、公私問わず様々な場面での需要があることから「死ななかった」と言ったのだと思います。
確かにそういう意味では生存しているし、その要因はきっと写真という分野が様々な変化をしながら、他のいろんなメディアと混ざり合い、新しい価値を生み出しているからでしょう。
ただ、僕は引っかかる部分があります。
一枚の写真を撮るのに数十分かかり、被写体の人が同じ姿勢を保つために”首おさえ”という金具で頭を支えながらポーズを取っていた時代と比べては元も子もないですが、誰もが手の中に収まる小さな箱でいつでもどこでも写真を撮影し、様々な加工も簡単にできて、撮影から数分でそれを世界中に発信までできる。
とてつもなく大きいことができるようになったのに、さらにそれが一般の人の手の中で完結できる。
ここまでの大きな変化があったのに写真の本質は変わらず存在しているのかなと僕は疑問に思ってしまうのです。
写真の本質とは
では写真の本質とは何かということに向き合っていきましょう。
写真の本質ついて考えるようになったのは僕が写真館で働き始めてすぐの頃のことです。
料金を払っていただいて写真を撮影させてもらっているにもかかわらず、僕は人が写真館に写真を撮りに来る理由が全くわかりませんでした。
なんとも失礼な話です。でも意外とそんなカメラマンはいるのかもしれません。写真が好きでカメラマンとして身を立てて行きたいけれど、写真家として仕事をもらうのは簡単なことではなく、とりあえず写真に携われる仕事でと写真館に就職するという人も結構いました。
そんな人は大抵すぐ辞めてしまっていたけれど。
僕はもともと写真が好きで始めたわけではなかったので「俺はこんな写真が撮りたくてカメラを手にしてるわけじゃないんだ!!!」的なことは全くなく、ただひたすら自分が撮影したものを決して安くはない金額を払って購入していくお客様に対し、恥ずかしくないものを残すことに必死でした。
だから「人は何故写真を撮るのか」の理由をぜひとも知らなければならなかったのです。
それを教えてくれたのはやみくもに読み漁った写真関連の本の中の1冊と、今も良い友人として交流のある当時のお客様でした。
ここでいきなり話が横道に入りますが、みなさんに問題です。
自分の家に好んで絵画を飾る習慣があるとして、(好きな歌手のポスターとか、アニメのフィギュアの方が想像しやすいかも)
部屋を飾るという概念があるにもかかわらず、写真を飾る人が少ないのはなぜでしょう。
日本人には特に当てはまるのではないかなと僕は思っています。
唐突なクイズを出題されて困惑されているかもしれませんが、答えを考えていただきながら本題に戻りましょう。
前の項目で話したその本とは「明るい部屋 写真についての覚書」ロラン・バルト 著 花輪 光 訳 みすず書房 です。
この著書の中でロラン・バルトは写真の本質を〈それはかつてあった〉とあらわしています。
僕は写真を語る上でこれ以上端的に過不足なく表現している言葉を知りません。
写真とは目の前にある情景がかつて存在していたということを表現する媒体であるというのが全てだと僕は考えています。
そんな身も蓋もない、味気もないものなのかと言われそうですが、深く深く深淵に潜り込んでいくとこの言葉にたどり着くと思います。
ではこの言葉とともに人が写真を撮る理由について考えてみましょう。
あなたはカメラを渡されて自由に写真を撮ってくださいと言われたら何を撮りますか?
そんな質問をされなくても現代の人々はほぼ誰もが手にしているスマートフォンのカメラ機能で写真を撮る「自由」を手にしています。
なのでご自身のスマートフォンに保存されている写真には何が写っているか確認してみてください。それがそのまま、写真を撮る理由に繋がっています。
人が写真を撮る理由
家族や友人と撮った写真、綺麗な景色を写した写真など、様々な写真があなたのスマートフォンの中にあると思います。
あなたは何故その写真を撮ったのですか?
大好きな存在が目の前にいる時間、感じている幸せをカタチに残したい。
きっとそれが答えだと思います。
人は必ず「過去」を持っています。その過去に縛られて苦しんでいる場合もあるでしょうが、「過去」が今の自分やこれからの自分を支えてくれていることも大いにあるでしょう。
つまり写真を用いて美しい過去をいつでも振り返られるようになる。これが写真を撮る理由だと思います。
それを実体験として教えてくれたのが先に話した友人達でした。
勤めていた写真館には子供の成長と家族の姿を残すためにたくさんのご家族がきてくださいました。
家族が始まった時から、お子さんが生まれ、外に写真を撮りに出かけるまで育てるという時間の中にも大きな困難や苦悩があったことでしょう。
その話を聞きながらカメラを通してその人達に向き合ったとき、僕の抱えていた疑問は解けました。
大切な人が目の前にいることの証を残し、これからもそれを増やしていこう。その気持ちが写真に重ね合わさっているのです。
なにをわかりきったことを改まって書いているんだとおっしゃる方も多いかもしれませんが、僕が育った家庭では写真館に行くという習慣がなく、初めて家の中で飾られていた家族写真は妹の結婚を機に行った沖縄旅行で僕が三脚を立てて撮った一枚だったのでお客様が見せてくれていた景色が自分にも重なった瞬間はとても新鮮な感動でした。
そんなことあたりまえだよと知っていること自体が実はとても幸せなことなのかもしれません。
ここでまた余談ですが、僕の両親が写真をまったく残さなかったかというとそうでもありません。
僕が写真を仕事にしていることをきっかけにフイルムカメラを手にすることもあり、父から昔使っていたオリンパスのOM-1というフイルムカメラを譲り受けました。
今のデジタルカメラよりも操作が難しいカメラで家族を撮ってくれていたこのカメラは、今はもう故障してしまって撮影はできませんが大切に持っています。
写真とその他の表現との違いとは
さてここで本題の一つの締めくくりとしてクイズの答え合せをいたしましょう。
何故部屋に写真を飾る人が少ないのか?
少ないのかとしたのは、時代の移り変わりとともに変化して写真を飾る文化が少しずつ日本にも浸透しているかもと思ったからです。
そして飾っている人の多くはおそらくご自身の家族や友人との写真でしょう。または思い出の景色を写した風景写真かもしれません。
それらの写真なら飾らない理由は日本人にありがちな「照れ」だったり、飾りたくとも住宅事情で飾るスペースがないとかそんな理由でしょ、となるかもしれません。
ではここでいう飾られない写真とは。
それは自分と全く所縁のない知らない人の写真です。
知らない人の写真を飾る理由なんてないでしょ。何言ってんの?と言われるかもしれませんが、絵画に置き換えるとどうでしょうか。
竹久夢二の美人画やドガの描くバレリーナの絵ならばどうでしょう。
それらは実在した人たちや情景をモデルにしていたとしても、デフォルメされていたり、画面の中で再構成されている”作られた”景色だから別物だと言われるでしょう。
裏を返せば写真はカメラの前に立つ被写体の存在と強く結びついているため、たとえ印画紙にプリントされた平面の世界だったとしても写真を見る人と写された人との関係性が強く影響するのです。
いくら赤ちゃんが可愛いからといって他人の子供の写真を部屋に飾ったりはしませんよね。我が子の可愛い姿だから部屋に飾りたい。
当たり前の感情ですが、ここが他のメディアと写真との大きな違いです。
観賞する人の個人的な感情がその写真の価値に大きく左右されるという特殊な表現媒体なのです。
もちろん写真も一つの芸術として作品を世に出しているひとも多くいますが、世の中に生み出される写真の数に対して考えると、客観的に評価されている写真よりも個人的(本来対になるのは主観的という言葉でしょうが)に評価されて飾られる写真の方が圧倒的に多いと思います。
つまり人が大切なものとのつながりをカタチにしたいと思う気持ちがなくならない限り、写真という手段が選ばれる機会はなくならない、「写真は死なない」ということになるのです。
似たようなことが動画にも言えると思われるかもしれませんが、動画はまた違う要素を含みますし、異なる特性もあるため、写真とは同一にはなりません。
この話はまた別の機会に話せたらと思います。
さてこれで友人からもたらされたテーマに一つの答えが出せたと思います。
先ほど”一つの締めくくり”としたのも、今、”一つの答え”としたのも理由があります。
最初にも書きましたが、僕の考えの中にある「本当に写真が死んでいないのだろうか」という部分には触れられていません。
ここまででも想定していた以上に長くなってしまっているのでこれについてもまた続きという形で改めて書いていこうと思います。